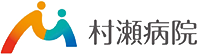外来・診療科目
循環器内科
治療方針と主な診察内容

循環器内科は、高齢者に軸足を置いた生命予後、ADL・QOLの改善などを目的に治療方法(薬物療法、カテーテル治療、外科治療の選択の決定)、健康寿命維持等、一人ひとりに合わせた治療/ケア設定をしています。
年齢とともに、心臓・血管系疾患は増加します。
高齢者の心臓血管の特徴と疾患を少し解説させていただきます。
すべての心臓病が進行して陥る心不全は、75歳を過ぎると急速にその頻度を増してきます。
高齢者の心不全の年間発症率は64歳以下に比べ、男性で3倍、女性で4倍になります。
しかも、症状が消化器症状、意識障害、精神症状等の胸部症状ではない非典型的症状であることも多くあります。
長期臥床のため症状が出にくかったり、認知症で訴えがわからないことも多くあります。
以下に、代表的疾患を例に挙げて解説します。
心筋梗塞では、胸痛発作は高齢者では減少し、意識障害や消化器症状での発症が増加します。また、女性の発症頻度が増加します。
心筋梗塞に伴い、各臓器の予備力が潜在的に低下しているため、呼吸器、腎臓をはじめとする多臓器の障害を合併してきます。
心臓の老化を病理学的に調べますと、男女共に老化による重量の増減はなく200〜300gの正常範囲にありますが、長期臥床や低栄養が重なると、重量は200g以下となり、すなわち、心臓が弱ることになります。心筋にはアミロイドという変性タンパクが沈着し、20%〜40%に証明されます。心アミロイドーシスと診断される方は少ないですが、専門的観点からは少なくない疾患で、心臓の働きを著しく障害します。
心臓弁は血流の機械的刺激を受けやすく、次第に肥厚、硬化し、石灰化します。
特に大動脈弁は変性傾向が強く、石灰化はその付着部におこり、大動脈弁狭窄の原因となります。
刺激伝導系(電気系統)の変化では、発電所である洞結節は線維化と脂肪浸潤により小さくなり、洞結節の特殊細胞の減少がみられ、20歳代の面積の1/3〜1/4となります。
心房細動という不整脈も高齢とともに急速に多くなります。
心房細動は脳梗塞の半分を占める心原性脳梗塞の原因疾患ですが、その70%は、75歳〜85歳の間に発症します。
心臓と腎臓は加齢の影響を最も受けやすく、この2つ臓器は密接に機能分担していますので、心臓と腎臓は一つの臓器として治療する必要があります。
また、悪性腫瘍の合併や、肺炎、慢性閉塞性肺疾患の合併も日常的にあります。
すなわち、高齢者は、循環器医専門医の立場でなく、全人的医療の観点でみる必要があります。
本院は、このような高齢者の心臓血管疾患の特徴/背景を十分に考えて、痛みを伴う観血的/侵襲的検査をなるべく避けて、CT、MRI心エコー等の非観血的検査で診断し、年齢に沿った治療を実践するように心がけています。
すでに多数の内服薬をのんでいる方も多く、当然、その副作用による症状も多いため、服用薬を総合的に見直し、必要最小限になるように薬剤管理も心がけています。
本院循環器科は、高齢者の心臓血管疾患について、診断/治療/長期生活の質の観点から一人ひとりの最良の医療/ケアを模索し、健康寿命の維持をめざした全身管理、医療からリハビリ、介護まで、多職種連携して最良のものを提供していきたいと思っています。